「」 に対する検索結果 : 26649件

江戸末期から明治初年にかけての大和型船の面影を伝える。全長2.7mの大型模型。明治維新前後の製作と思われろ。 その後よく補修されて保存良好である。帆装等は後に取り換えられたようで、船体はもちろん、両側の舵腹をはじめ船内の艤装もよく残っており、当時の和船の詳細を知ることができる。年代:江戸末期~明治初年
情報所有館 : 神戸大学 海事博物館 ![]()

江戸時代に日本独特に発達した羅針盤である、北をさす磁石に対してを進行方向の船首を12支(実際は24方位)の角度で知ることによって、針路を定めていた。年代:江戸時代中期
情報所有館 : 神戸大学 海事博物館 ![]()

沖縄本島の沿岸で貨物輸送に使用されていた。沖縄は江戸時代中国南部との交流があったため、船も中国船に似ている。この模型は2.1mあり、山原船末期にあたる昭和初期の型式を示している。年代:昭和初期
情報所有館 : 神戸大学 海事博物館 ![]()

大正末年帆船に小型焼玉エンジンを積んで、港の出入りや無風時に利用する機帆船が現れた。この模型は二次大戦前の機帆船最盛期の姿を示している。年代:1930~40年代
情報所有館 : 神戸大学 海事博物館 ![]()
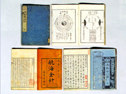
博物館蔵書の中で和漢の航海や航路に関する指針の3点です。航海金針は1853年(咸豊3年)に中国で出版されました。他2点は江戸時代日本で出版されたものです。年代:1853年(咸豊3年)
情報所有館 : 神戸大学 海事博物館 ![]()

江戸大阪間の海路を画いた大図。特に紀州沿岸は拡大して画かれ、暗礁の所在、港の出入にあたっての注意事項などを極めて詳細に記入してある。幕末異国船が日本近海に出没し始めた頃、いつ出動を命じられても困らないように、紀州藩のお舟手が江戸までの沿岸を調査して作ったものではあるまいか。
情報所有館 : 神戸大学 海事博物館 ![]()

薄い板を張り付けて船の形を表現した珍しい額で、絵馬に較べると奉納された地域が限定されている。極少数ではあるが船体の半分を作って板に取り付けたものもある。鍋屋正兵衛の銘あり。年代:文政7年(1824)
情報所有館 : 神戸大学 海事博物館 ![]()

和船の各部寸法比率はほぼ一定していたため、船大工は板に側面図を画くだけで詳細な図面は作らなかった、使用済みの板図は削って次の船に利用したため、古い板図は余り残っていない。
情報所有館 : 神戸大学 海事博物館 ![]()