「」 に対する検索結果 : 26649件

《特記》 角型 《呼称寸法》 1尺4寸 《銘》 <切>中谷□□作/請合 《材質》 鋼/タラノキ 《寸法》 幅140×長640×厚・高32 mm 《時代》 《産地》 国内
情報所有館 : 竹中大工道具館 ![]()

《特記》 天王寺型 《呼称寸法》 2尺2寸 《銘》 <切>中屋吉蔵作 <印>山形国の光□山形県最上郡及位駅前/特製安来鋼黄紙 《材質》 鋼/タラノキ 《寸法》 幅270×長1000×厚・高45 mm 《時代》 昭和20~50年(1945~1975) 《産地》 山形
情報所有館 : 竹中大工道具館 ![]()

《呼称寸法》 1尺8寸 《銘》 <印>登録商標□ <裏切>難波 《材質》 和鋼/タラノキ 《寸法》 幅380×長860×厚・高48 mm 《時代》 不明 《産地》 大阪
情報所有館 : 竹中大工道具館 ![]()

ガソリン自動車の第1号は、各国でさまざまな説があるが、いちおうベンツが1886年につくった3輪自動車といわれている。小型で軽量なエンジンを開発していたカール・ベンツは、これを馬車に代わる新しい乗り物に用いることを考えたが、操舵性に問題があり、はじめ3輪車を設計、ティラー(棒ハンドル)で前輪を操向する方法でこれを解決した。リアアクスルの上におかれた工ンジンは水平単気筒、時速15kmの走行が可能で、デフを備えていた。 1886年
情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

3輪車を一歩進めて4輪車の設計を開始したベンツは、まずキングピン式の前輪操向システムで、1893年にドイツ帝国の特許を取得。これを採用してつくられたベンツ最初の4輪車が“ヴィクトリア”であり、ひと回り小さい“ヴェロ”は1894年に発売された。フライホイールが垂直になるようにエンジンがセットされ、プーリーとベルトによる2段変速機からデフを介してチェ-ンで後輪を駆動、時速21kmで走行できた。 1894年
情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

パリのド・ディオン・ブートン社は1883年からスチームカーを生産していたが、1895年からガソリン車に転向。軽量で信頼性の高いエンジンを開発し、先ず三輪車に搭載、その機動性、低価格でたちまちヨーロッパ市場で最もポピュラーな車に仕上げた。1898年には前部に客用シートを備えた改造四輪車も追加。しかし市場からの乗車定員増、乗客の安全性、快適性等の要求には応えられず、次第に市場を失い、三輪車、改造四輪車ともに1903年には生産が打ち切られた。 1898年
情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

オールズモビルも1890年からつくっていた蒸気式3輪自動車に代わってガソリン自動車を1895年に完成させたが、注目すべきことは1901年に発表したカーブドダッシュで、世界初の大量生産方式を採ったことだ。1902年には2500台、1903年には4000台、1904年には5000台が売られ、当時のヨーロッパ最大のメーカー、ド・ディオン・ブートン社の年間1200台の生産台数と比較しても、この数字の重要性がよくわかる。 1902年
情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()
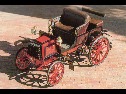
当時のパイオニアカーのほとんどが馬車や自転車などの影響を受けて、まだ駆動系のレイアウトや機構は“馬なし馬車”そのものであった。この点からすれば、1899年から自動車製造を開始したパナール・ルヴァッソールかダイムラーの鋼製自動車(1888年)をヒントに考案して、1891年にパテントを取得した機構が自動車技術の基礎を築いたことになる。いわゆる最先端に置かれたエンジンの後方に、クラッチ、トランスミッションを縦一列に配し、ドライブシャフトとデフ機構を介して後輪を駆動させるFR方式を採った最初の自動車なのである。このモデルは、初期のティラー式から、すでに円形ステアリングホイールと傾斜したステアリンクコラムを持ち、アッカーマンの方式を採用している。 1901年
情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

ピストル製造で有名なコルト社出身の精密技術の権威ヘンリー・M・リーランドはデトロイト・オートモビル社を経て、1902年にキャデラック社を創立。最初に完成したのが“モデルA”である。設計はデトロイト・オートモビル社時代のヘンリー・フォード。エンジンはリーランド&フォークナー社がオールズモビル用に生産していた水冷単気筒で、これに遊星ギアを組み合わせ、前進2段と後退1段のギアボックスを備える。ラジエターは熱気が乗員に当たらないように、やや引っ込めて取り付けているのが特徴で、フレームは鋼鉄製、量産体制もこの時できあがっていた。 1902年
情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()

ガソリン自動車の普及がはじまっても、アメリカでは長い間、電気自動車がつくられた。それは、やはり1895年にジョージ・ウィリアム・セルデンが取った自動車そのものに対するパテントのため、ガソリン自動車をつくるためにはロイヤリティを支払わなければならなかったからだろう。しかし、もうひとつ考えられる理由は、静かで、排気ガスもなく、始動時にクランクを回す必要がないという電気自動車の利点によるもので、事実、女性には人気があったという。ベイカー・エレクトリックは1899年から1915年まで続いた有名な電気自動車で、1馬力のモーターから時速40kmの走行が可能。各部にボールベアリングを多用し、初めて駆動系にベベルギアを採用したことでも有名である。 1902年
情報所有館 : トヨタ博物館 ![]()