「明治大学博物館」 に対する検索結果 : 80件
情報所有館 : 明治大学博物館 ![]()

固化に時間を要するという漆塗り製品の弱点を補うため、加熱によって固化を早めるため開発された。また、花瓶の器胎には一定の自重も必要なことから陶胎は恰好の素材となった。その後、合成漆器の品質向上と生産体制の整備、プラスチック器胎の普及などによって衰退したと考えられる。1959年収集

日常に使用する汁椀には合成漆器の普及が著しかったが、品質を向上させつつ、家庭経済の上昇にともない少々の見栄えと贅沢を意識した高級品に昇華する商品も一方に存在した。そういう意味で、高度成長期は伝統的工芸品産業にとってネガティブな環境ではなかった。家庭における来客接遇機会の増加による需要の増加に対応した商品。香川漆器の中でも実用的な堅牢度の高い製品。1960年収集

増え続ける需要に応えるため、会津や山中などの主要産地では量産に適した合成漆器の製造が模索された。本製品は木胎ながら、伝統的な本堅地下地ではなく、当時普及し始めていた合成下地を施したもので、上塗りもカシュー漆の可能性がある。1961年収集

漆に色素を混ぜ粘土状に固化させた堆錦餅を貼り合わせて装飾している(堆錦技法)。糸尻内に「琉球塗」の銘があるが宮崎県産。鹿児島県と同様に第2次大戦中に疎開してきた沖縄出身者の内、残留した者に対する授産事業として琉球漆器の技術者が指導した。宮崎県(製造者不明) 1963年収集

増え続ける需要に応えるため、会津や山中などの主要産地では量産に適した合成漆器の製造が模索されたが、その普及が進む1960年代にかけては、まだまだ在来の手工芸製も実用の普及品であった。砥の粉と生漆を混合した塑型材である錆地を盛り上げて竹の節を表す表現技法。1964年収集
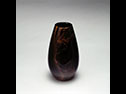
水の上に流した漆をすくい取って器面に写す、「墨流し(マーブリング)」の技法を漆芸に応用している。第2次大戦後、宮城県の鳴子(現大崎市)出身の漆芸研究家沢口悟一が1950年代前半に考案した。経済産業大臣指定伝統的工芸品鳴子漆器の特徴的なデザインとしてよく知られるようになった。沢口漆器店1988年収集 他1961年から1988年の間に収集した4点計5点を収蔵

八幡馬(青森県)、三春駒(福島県)とともに日本三駒に数えられる郷土玩具。一人製作を継承していた菅野実が1998年に逝去したことにより一旦途絶えたようだが、現在は社会福祉法人希望の杜福祉会「工房けやき」が製造を継承している。菅野実(宮城県仙台市) 1997年収集

孟宗竹に朱漆をほどこしている。宮崎漆器と同様に第2次大戦中に疎開してきた沖縄出身者が製作に従事した。三越本店で購入したのは鹿児島県物産展の折と推測される。鹿児島県(製造者不明) 1958年収集

畳表の生産縮小にともない花筵生産へ転換がなされた時期の収集。物産カタログでは室内装飾品や身辺雑貨がアピールされているが、岡山県の藺草作付は1960年代後半から減少の一途をたどる。編目の美しさと藺草の素材感による造形は再評価がなされてしかるべきだろう。岡山県東京物産協会から購入。 岡山県(製造者不明) 1958年収集

畳表の生産縮小にともない花筵生産へ転換がなされた時期の収集。物産カタログでは室内装飾品や身辺雑貨がアピールされているが、岡山県の藺草作付は1960年代後半から減少の一途をたどる。編目の美しさと藺草の素材感による造形は再評価がなされてしかるべきだろう。岡田新太郎本店(岡山県岡山市) 1960年収集